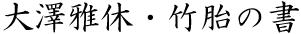私は無知無力である。私にはまだ思想といふ程のものがない。まだ子供なのだ。
19の秋、北海道へわたり、北見のルベシベといふ町で代用教員をし、月給36円いただいたのが、そもそもの私の貧窮行のはじまりである。よい詩作がしたいばつかりに、海を渡つて北海道へ行つた私なのだ。それはその通り詩歌のまねごとを作つてもみた。しかし見られるものは一つもない。マンドリンをひき、大黒座とかいふ芝居小屋をかりて10銭也の入場料をとつて音楽会なんかをやつたものだ。わざわざローソクをとぼして照明を暗くし、金ぶち眼鏡をかけてデアポロかなんか唄つた。マンドリン合奏の最中、絲が切れてしまつて相手のヴァイオリニストにまで汗をかかせたものだ。
ルベシベから兵隊検査で帰郷して丙種、まあ教育の方面をやつてくれ給へと言はれたことが耳底に残つてゐる。ついでに絵の検定を受けて合格、東京では50円しか貰へないから、それでは暮して行けないといふので再び北海道へ。今度はルベシベの隣村のオンネユといふところの学校。ここでは酒をのんで碁をうつて玉を突いて鉄砲をうつて、ヤマベ釣をしてお湯に入つて野球をして巾とびの選手になつて大会にひつぱり出されて尻もちをついて、6年暮して北海道がいやになつて帰郷して居候の身になつた。
しかし私はこの頃、子供の世界の美しさを発見した。童心の美、この世の中でもつとも美しいものは子供である。子供こそ大人の父だといふことを知つた。童画と童詩こそ私の魂のふるさとを見出さしめて呉れたのであつた。私は子供達と一緒に子供達とおんなじ画を喜んでかいたものだつた。提灯行列だのひろめや、紙芝居、かみゆひさんだの――今年の二科展に沢山扱はれてゐた画題のやうなものを。後に至つて私が童書の美を高く扱ひ、童書のやうな書を書くに至つて、誰が何といつても止められなかつた素因をなしてゐるのだ。人は私を竹胎童子とよくいふ。どうも私は子供の世界から一生抜けきれない人間なのかも知れない。
この頃貧しくて紙が買へないで家中の紙片をみんなあつめて書いてゐる。展覧会に出したあとのものなどに白いところが残つてゐるとそれを切り取つて皆かいてしまふ。障子紙へもみんな書いてしまつた。だから私の家の障子はどうも暗くていけない。今度は美術全集の裏をねらつてゐるわけだ。だから、友人が紙を持つて来てくれると何よりも嬉しくて忽ちのうちに書きつくしてしまふ。夜もひるもない。徹夜してもねむくはない寒くもない。つかれもしない。めしも食はずに二階にとぢこもつてしまふ。そして書きつくしてしまふと、とたんにしよんぼりとしてしまふ。ぼんやりと口もきかずにあらぬところを見つめて空ろである。紙に憑かれたとでも言ふべきか。狂人の部に入る資格があるかもしれない。
紙が欲しい、紙が欲しい。口には出さないが、さう思ひくらしてゐる私の眼の色は、はたで見てゐるにしのびないさうだ。だから紙を貰ふと、むさぼりつく如く吸ひついてはなれないのである。吸血鬼の如く。すつぽんの如く。そしてそれ程恋ひ焦れる紙に、何を書くのかといふと、まるで子供の書く字よりもまだ幼稚なものを書きまくる。それをかいてゐる時だけが私にとつては天国なのだそして悦に入つてゐるのだ。
狂人かな。私の知つたことではない。私は万年童心で居りたいのだ。
「書原」第23号(昭和25年4月発行)より抜粋
注* 表記は原文のままとした