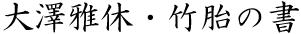私は大沢雅休氏にも、大沢竹胎氏にも個人的関係は薄かった。それは昭和20年、日本書道美術院が結成されこれには入ったものの22年の秋、書道芸術院が樹立されるとともに、同氏らが退会したからである。ただ両氏とも、感情は非常に豊かな人であると思っていた。
私は昭和24年11月、東京国立博物館応挙館・九条館において、当時の国宝、重要美術等、百三十余点の古名蹟の展覧会を開いた。私としては当時、日本固有の文化が社会動乱のために粗末にされていることを嘆き、古典の優れていることを日本人に自覚せしめようと思って開催したのである。何分にも当時の書道界というのは、高野切といったり、関戸古今集といったりしても、実物を見たことのない人が多かった。私はその会を開き、少しでも古典の真髄を皆さんに知ってもらおうと思った。
その当日のことである。たまたま出品されていた伝小野道風筆継色紙の前に、どっかとあぐらをかいた羽織、袴の巨漢が、いつまでもいつまでも動かないのである。あとから見にくる人に、かなり迷惑になっているので注意しようと思ったら、それは大沢竹胎氏であった。その真剣な眸を見ると、少し入れ変ってくれろともいえなかった。
やがて竹胎氏は私の傍にきた。
「私は今まで継色紙の一番いいという複製を尊重して、継色紙を理解しようとした。しかしその継色紙の複製本と、本ものの継色紙とは別ものであった。本ものはこんなにも息づくような微妙さがあり、そこから広がりが発揮されてゆくさまは実に見事である。継色紙の微妙で偉大な美というものは、今日、本物によってはじめて知ることができた」と私に礼をいった。竹胎氏が見ていたという複製本は木版刷りの本であった。木刷と写真版とは線質の表現がまるで違うものである。
竹胎氏の新らしい書道の根底にこれだけ深い洞察力をもって古典を見ようとしていた努力が払われていたことは、見事であるといわなければならない。この根底があってこそ、無雑作に押しこんだような文字の配列にも何がな上味のあるやり繰りが自然に出来るのであって、もとの空しいものには決して出来ることではない。
「書道美術」第246号(昭和51年10月発行)より抜粋より
注* 表記は原文のままとした