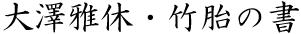私は中国や日本の書の歴史を深く研究したわけでもなく、また近・現代の書に通暁しているわけでもない。にもかかわらず、いま大沢雅休と竹胎の書について小文を記すことにしたのは、かつて平原社主催の遺作展で目にした雅休の「黒岳黒谿」のなまなましい感動が私の心によみがえって来たからである。
これは昭和28年、つまり雅休が死の年に日展に出した依嘱出品作であるが、日展側から陳列を拒否されたという曰くつきの作であることを、このとき私ははじめて知ったのである。
さて私は、雅休の晩年の作品の幾つかを見たにすぎないが、この「黒岳黒谿」の前に立ったとき、こうした背景の美術思潮はおろか、日本の書壇のさまざまな流派を超えて、直截にこの書が私の胸を打ったのである。これは書体からいえば篆書といえるのであろうけれども、いま数千年の歴史を一挙に現代によみがえらせ、その厚い肉質の書線と、ゆるやかに胎動する形態が、いかにも山そのものを彷彿させるのである。大きな歪みをもちながら、内部構造を離れがたく連結させ、泰然と大地の上に安定しているのである。
現代は読む書から見る書に移行したといわれるが、私たちはこの巨大な四文字をまず眼に見、次で読み、解き、さらに作者がこの書を托した心のうちを読むこともできよう。そしてまた文字のあいだの余白一面に、にじみやかすれを抱えた点と線が飛び散っているのは、大気に充満する眼には見えぬ粉塵を、リアルにあらわしているようにも思えて絶妙である。
しかしこの2年前の日展出品作「洞中仙草」では、そのしなやかに流動する線状が、仙洞の微風にそよぐ水草の形状を思わせ、大法というような概念をモチーフとしたものではなくて、自然の形態をモチーフとした文字の特質を的確にあらわしているのだ。ここに書の可能性を極限まで探求した作家の心意と、そのすぐれた技法が明らかにされている。
また雅休は「秋の日のヴィオロンの」ではじまるヴェルレーヌの詩や、草野心平の「かへるのうた」に触発された作品をのこしている。いま私は生前の雅休を知らぬまま、その遺作から逆にこの書家の全貌を類推するのであるが、棟方志功が「鬼のような人、仏のような人、神たるような人」と評した人がらを、私の熟知していた棟方志功と二重写しにして楽しんでいるのだ。貧しい農家に生まれ、野草、野鳥を愛し、歌、俳句、また小説も書いた。この人の内面には、野性と風雅がまさに共生していたにちがいないと想像されるのである。
(美術評論家)
「定本 大澤雅休・大澤竹胎の書」教育書籍(昭和56年発行)より抜粋
注* 表記は原文のままとした