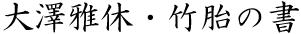雅休・竹胎ともに、文学や絵画、音楽などあらゆる手段でそれぞれの内面にある世界を表象しようとしていた。書はその手段の一つとして、そしてその最善のものとして選択された。したがって彼らのなかでは、書に関する規範や技術は、表現のための一要素であって、その修練自体に深い意味を持たせているようには見受けられない。書の古典に関しても、彼らはそれを習うための対象としてではなく、絵画などの確立された美術を鑑賞するのと同じ目線で捉え、深い見識を蓄えた。古典に内在する美は彼らの中で再構成され、他の諸要素と融合されて「現代」に見合った作品となった。兄弟と棟方志功がお互いの芸術に惹かれ合い、親交を持ったことも表現に内面性を強く求めた彼らの心情の表われかもしれない。また、高い技術力を持ちながら、時として稚拙とさえ思える作品を生み出したことも、その精神に反するものではなかった。
雅休が戦前の胚胎期を経てその精神を昇華させ、独特の形の作品を発表し始めるのは、昭和24年の日展依嘱作「華下草上」や第2回書道芸術院出品作「洞中仙草」の頃からである。この時から、昭和28年、没後に日展の依嘱作でありながら陳列拒否にあった「黒岳黒谿」まで、雅休独自の書による現代書壇への問いかけは続いた。
雅休とともに歩みを進めた竹胎であるが、兄雅休と思想の上では似通ったものを持ちながら、作品制作に関しては独自の道を歩んだ。その師、高塚竹堂のもとで卓抜した技術を身につけた一方、変体仮名を使わない単体表現を主にしたいわゆる「竹胎仮名」を生み出した。その単純化された線質と構成の代表的な作品とも言えるのが「ふるさと」や「はるのぬに」「くろつち」などである。また、木版や木彫などにも文字を題材としたものが目立つ。
(成田山書道美術館 学芸員)(現 大東文化大学 教授)
「大澤雅休・竹胎兄弟とその門流展」図録( 1999年発行)より抜粋
注* 表記は原文のままとした