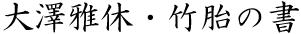大澤竹胎が、兄の大澤雅休とともに近代書の芸術活動に果たした役割は、かなり大きなものであったと思われるのだが、雅休ほどの知名度がない。それは、かな作家として出発し、かなをベースとして近代書の造形美を求めたにもかかわらず、それを完成した形として世間一般に認識させることができずに没してしまったからであろう。しかし現存の、竹胎が新しい書の創作を試みた作品に共通して、平安時代のかな美が垣間見えている。それらの作品には、さまざまな表現があり、一見全く異なる創作活動をしているようであるが、作品の底辺では、古典のかなに見られる造形美を、巧みに現代書に利用しているのである。
それらのひとつひとつを分析解説することはここではできないが、作品としての〈いろは〉と、おそらく手習いの手本であった〈いろは手本〉を較べるとよいであろう。〈いろは手本〉の一字一字が、どれもしっかりとしたかな文字であることは誰もが納得するはずである。これほど一字がしっかりとしたかな手本を、他に見たことがない。あくまでも古典から竹胎が学んで習得した成果であろう。ことに「く」や「と」など画数のきわめて少ない文字の存在感は見事である。これは、〈高野切〉第一種巻頭断簡の和歌に見える、「と」や「ゝ」などの点面の少ない文字の力強さに似ている。おそらく竹胎は、古典の画数の少ない文字、点や単純な短い線に見られる力強さに重要性を感じていたに違いない。
それらを踏まえた上に〈いろは〉を制作しているのである。これは、古典のかなの線の細さを意識し、字形を新しくしたものに違いない。よほど自己を超えない限り、〈いろは手本〉に見られるような習熟した「いろは・・・」であれば、よかれ悪しかれどこかに古典が現れてしまうのが一般的であることを考えれば、一見したところに、古典を感じさせない新しい造形を創り上げていることに、驚きを感じざるを得ない。
(五島美術館 学芸部長)
「書に遊ぶ」7月号(平成13年7月発行)より抜粋